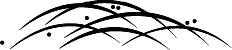

更新:2022-10-30
現在まで歌い継がれている
2つの学校の校歌を紹介します
旧府立五中・旧小石川高校・小石川中等教育学校 校歌
作曲 北村季晴
大正8年 (1919)
尊のみいつ吾嬬路に 古りし歴史は二千年
今将た仰ぐ帝城の 武蔵の国ぞ大いなる
二 流れも清き多摩川の 水にあらひて生れたる
男心は東海に 聳えて高き不二の山
曙近き人の世の 彼方の空ぞなつかしき
三 豊島の里に程近く 樹立も深き岡の辺に
結ぶや少き人情 吾学びやの開拓に
理想の鍬を振り上げて 二つの腕の勇む哉
四 源遠き文明の 科学の道に分け入りて
一もと咲ける野の花の ゆかりの色を翳す時
立つるやここに創作の 真理をきそふ志
五 菅の荒野を飛ぶ鷲の 羽風も高き飛騨の山
白雲遠き高原に 行く手の森を眺むれば
小草の露に命あり 吾踏む土に力あり
六 平和の光今更に 五洲の海に輝きて
恵の波のいやひろく 八洲の外に布くところ
振はんかなや開拓の 吾が校友の精神を

作曲者の北村季晴(きたむら すえはる)は 明治学院で島崎藤村と同級 明治32年11月長野師範に転任したのが縁で「信濃の国」に第二の作曲し 長野県民を魅了した
季晴は進取の気象を終生持ち続けたといわれ その点で伊藤長七と相通ずものがあったと思われ 小諸で親交のあった島崎藤村を介して作曲を依頼したのかもしれない 季晴は昭和6年6月60才で没した なお 季晴の8代前の季吟は高名な古典学者で 松尾芭蕉は弟子だという

撮影:2013-10-05 於 日比谷公会堂
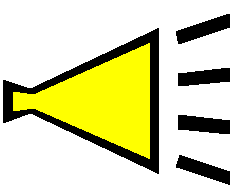 下の ▶ クリックで mp3ファイル読込後に再生
下の ▶ クリックで mp3ファイル読込後に再生旧諏訪中学・諏訪清陵高校・同左附属中学校 第一校歌
作曲 田村幾作
明治36年 (1903)
大和島根の脊梁と 信濃にしるき秀麗の
湖山の中に聳え立つ 吾が学び舎を仰がずや
二 春城上の花霞 白帆のかげもほのかなる
衣ヶ崎の朝ぼらけ 芙蓉の峰を望みては
昔忍ぶの石垣に みやびの胸の通ふかな
三 夏は湖水の夕波に 岸の青葉をうつしつつ
オール執る手も勇ましく漕ぐや天龍富士守屋
げに海国の日の本の 男の子の意気ぞたのもしき
四 唐沢山に秋長けて 御空も澄める運動場に
思へば遠し千早振る 建御名方の英霊や
絶えて久しき大神の 武健の腕を鍛へばや
五 冬綿嶺の山の雲 吹雪ぞ荒るる北風に
堅氷鎖す方十里 もしそれ月の色冴えて
学窓書に親しまば 吾が雄心の湧かずやは
六 見よ千頃の田園や 煤煙つづく製糸場
世界の富を集めては 国の基を興さんも
希望にみてる青春の 我等を措きて誰かある
七 思へや汽笛中央の 鉄路に沿うて響きつつ
心は駆ける五大州 理想の岸は遠くとも
日に新たなる進運の 学びの道に後れめや
八 それサクセンの林中に 独逸の国の力あり
き流れはアルプスの 深き谷より出づとかや
ああ信山の健児らの やがて咲くべき春や何時
本校歌を作詞したとき 伊藤長七は東京高等師範学校の学生(27才)であった

第一校歌を熱唱する卒業生
撮影:2008-06-08